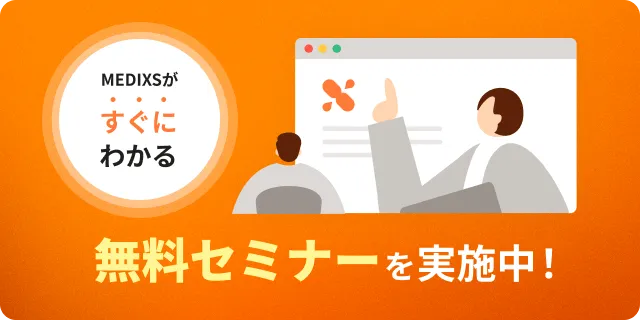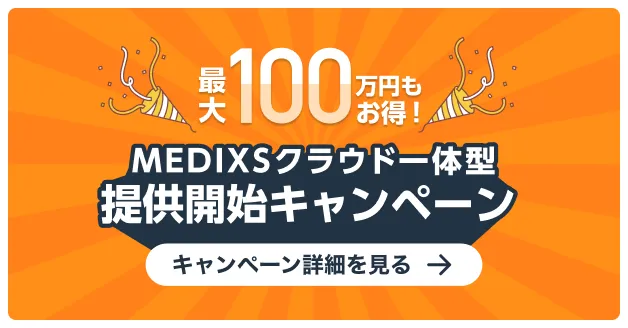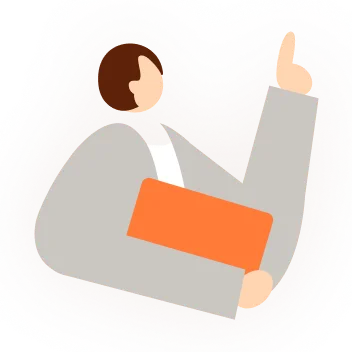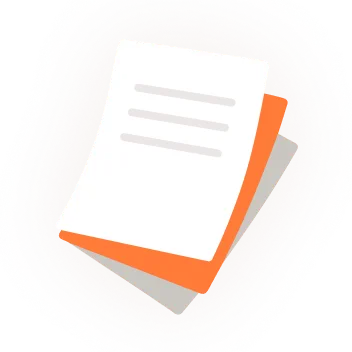Blog
Amazonファーマシーが国内サービスを開始。薬局への影響と対策
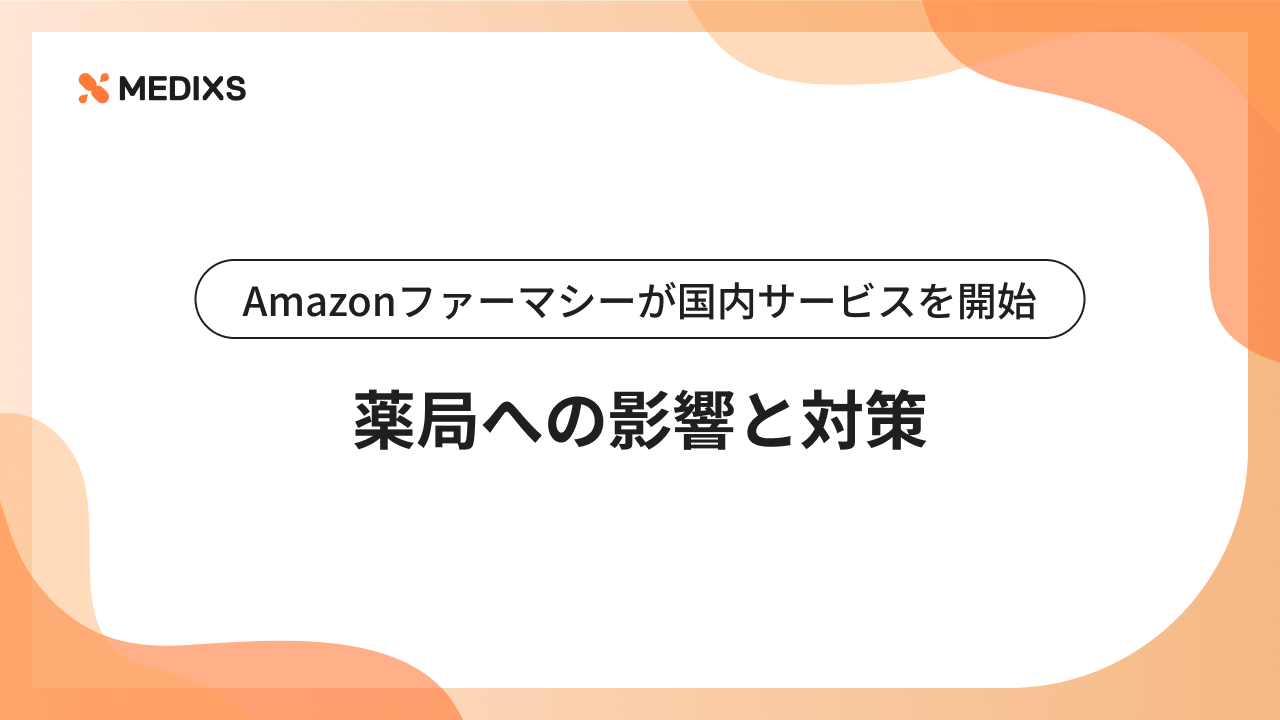
2024年7月23日、日本でのAmazonファーマシーの開始が発表されました。この記事では、Amazonファーマシー開始に伴う調剤薬局への影響や、薬局の存在価値、患者さんから選んでもらえる薬局づくりという観点からどう対応していくべきかを考察します。
Amazonファーマシーの概要
Amazonファーマシーは、オンラインで薬局から処方薬を購入できるサービスです。 薬剤師による服薬指導をオンラインで受けられ、処方薬を自宅など指定の住所に配送または薬局の店舗で受け取ることができます。【出典1,2】
調剤薬局への影響
結論から述べると”現状”ではAmazonファーマシーは今すぐに業界に影響は与えるものではないでしょう。
理由としては大きく分けて3点あります。
- すでに似たサービスがリリースされている
- 電子処方せんの普及が追いついていない
- 診療からの過程を考えるとすごく手間
それぞれについて解説します。
まず、オンライン服薬指導のツールやアプリなど、似たサービスがすでにたくさん存在しています。他のサービスでは紙の処方箋を気軽に利用できるのに対し、Amazonファーマシーは電子処方せんのみの利用となっています。これはおそらく、処方せんの原本回収のリスクを回避するためだと思いますが、薬局での電子処方せんの普及率が現状2%台であることを考えると、すぐに利用される状況ではないと思います。
また、多くのプラットフォームは医師によるオンライン診療と組み合わせられており、比較的 "診療〜薬の受け取り”までの動線が出来上がっています。
しかし、Amazonファーマシーの場合、診察を受ける際にはAmazonファーマシーアプリから別のアプリに移動し、そこで診察を受けてからAmazonアプリに戻り服薬指導を受けるという流れになるため、患者さんにとっては少し手間がかかる仕様です。
このように現状では、患者さんにスムーズな医療体験を提供するのは難しい状況です。ただし、これらはあくまで現時点でのサービスの状況です。今後、これらの問題が解決された場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
“Amazonのアプリで診療を受けることができ、そのまま薬が患者さんの手元に届く”
既存のものがあるとはいえ、これだけでもインパクトがありそうではないでしょうか?
2021年時点でAmazonのユーザー数は5,120万人です。【出典3】
まずは、これまで「診察を受けて処方せんをもらう」という行動をしてこなかったライト層がこのサービスを利用する可能性が非常に高いでしょう。
現状でもオンライン”診療”の新患だけでも200〜300人毎日診ているクリニックもあるようなので、糖尿病内科、心療内科、アレルギー科など比較的定期薬が変わらない患者さんは、気がついたらどんどん流れていってしまう可能性があります。
調剤薬局としてのあり方とは
では今後、どのような未来が予想されるでしょうか?
集客について、顧客(あえて患者ではなく顧客とします)が真に求めているものをしっかりと考えていかなくてはなりません。
「適切な患者対応をすれば患者が減ることはない」という話があがることもありますが、今後の医療の流れの変化を見ていると、顧客がオンラインに流れてしまう可能性は高いでしょう。
全国薬局患者満足度調査の論文によれば、調剤薬局に顧客が求めていることは、待ち時間の短さ、立地、スタッフの接客対応です。【出典4】
特に、顧客が利用したくないと思った理由で最も多かったのは、待ち時間の長さです。
そのため、利便性を求める顧客が、Amazonファーマシーに流れていく可能性はあるのではないかと考えます。
また、集客についても同様です。顧客が重視しているものは立地のため、立地が良くない薬局を時間をかけて探してまで、新しい顧客は来局しません。さらに言ってしまうと、門前の場合、通われる顧客の多くは目の前の病院、クリニックを受診された方が多いのではないでしょうか。
しかし、待ち時間が長くなってしまったり、立地に頼ってしまい、集客や顧客への対応を怠ってしまうと、気がついた時には顧客は離れていってしまいます。
今一度、この2点について見落としているポイントがないか、見直すべきなのではないでしょうか?
薬局として今後どう対応していくべきか
現在、DX化とよく言われていますが、それはなんのためのDX化なのでしょうか?
生産性を向上させるためのシステム導入などは積極的に行うべきですが、何のためにシステムを導入するのかをしっかりと薬局の運営まで見据えて考える必要があります。
コスト感覚にもよりますが、作業時間を減らすシステムは費用対効果の面で導入を推進すべきです。
ただ、”減らした時間を対物から対人へ”といいますが、対人サービスの提供内容はどうでしょうか?
ただ一人の患者さんに長時間の接客をするだけでは、先ほどの論文にもあるように、かえって逆効果になるかもしれません。
それであれば、顧客の待ち時間を減らすためのオペレーションや、集客のための施策を考えて実行するなどの対応をした方が良い循環が生まれると考えます。
Amazonファーマシーのスタートは、今一度顧客が真に求めるものが何かを、薬局が考えるいい機会になるかと思います。
【出典1】 Amazonファーマシーとは
【出典2】 Amazonに中小薬局はどう立ち向かうか
【出典3】 ニールセン、デジタルコンテンツ視聴率のMonthly Totalレポートによる オンラインショッピングのサービス利用状況を発表
【出典4】 患者が薬局に期待すること:全国薬局患者満足度調査
<著者プロフィール>
吉田大貴(株式会社pharb 新規事業開発部 責任者)
ドラッグストア、チェーン調剤薬局にてエリアマネージャーに従事。
施設在宅、M&A案件獲得のための営業を経験。
大学時代の友人に誘われ株式会社pharbに入社。
同メンバーにて新たに立ち上げた株式会社precalにて事業開発と営業責任者に従事。
現在pharbの薬局事業専任となりオンラインDSを目指し店舗開発運営をおこなっている。
- 当コラムの内容は、株式会社アクシスの見解ではなく筆者の見解です。
- 当コラムの内容についての責任は負いかねます。
- できるだけ正確な情報を発信するようにいたしますが、完全な正確性は担保できません。